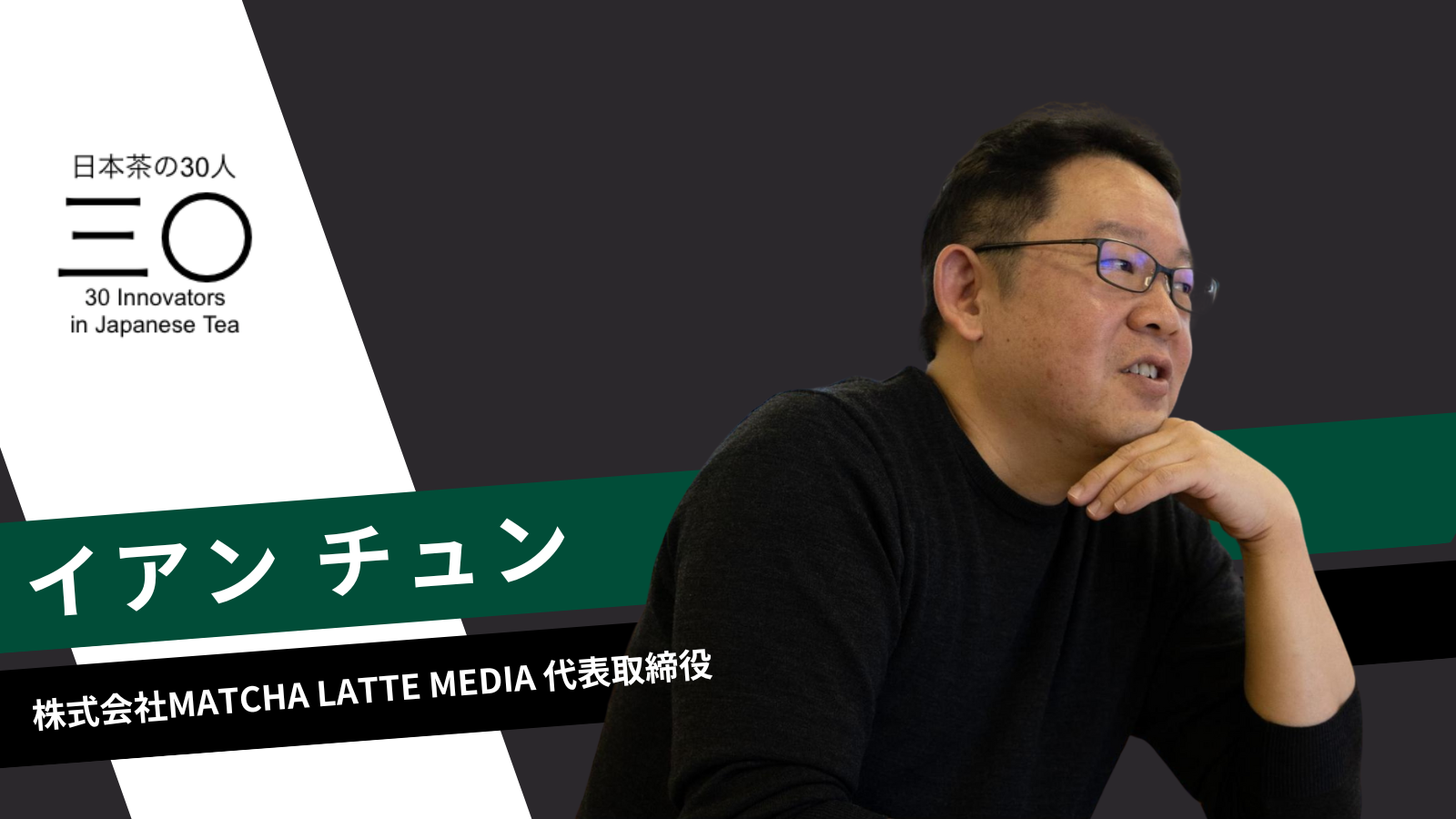プラハ ティーフェスティバル 2024
2月24日ー25日に第2回プラハティーフェスティバルが開催されました。さらに、イベント開催中の1週間はプラハにあるティーハウス周辺で様々なお茶の催しがありました。このフェスティバルの企画者 Agha さんのおかげでイベントの質はどれも非常に素晴らしい出来栄えでした。 このフェスティバルには多くのティーメンバーが参加するので、もちろん私たちも見逃せません! イベントでは、多くの素敵な催しがありました。そして、名だたる出展者や茶陶アーティスト達は、ヨーロッパからそしてヨーロッパ以外からチェコ共和国に駆けつけた沢山のお茶愛好家をワクワクさせていました。お茶愛好家にとってこのイベントは見どころが沢山あり、本当に語り三昧です!ただまず最初は私たちのお気に入りのトピック:日本茶に注目しましょう。 私たちは長崎いけどき代表者かつGJTea仲間のMarjolein Raijmakersさんと一緒に出展しました。彼女は長崎の東彼杵で採れるお茶を広めるためにヨーロッパ各地を周っていました。玉緑茶はここでの主役の一つかつそのエリアの名産品です。ブースではそれに加え、さまざまなほうじ茶の個性と温かさが、多くのお茶愛好家の心を魅了していました。また、不良品のお茶を使って染められた手拭いは早くも売り切れ間近でした! Rishe TeaのAreekさんはチェコ共和国でのお茶フェスティバルの常連さんです。彼は日本の茶産地を旅しておられ、彼のブースでは日本の有機栽培緑茶が綺麗に並べられていました。彼についに対面で出会えたのは光栄な限りです! 私たちの友、フィンランドにあるNari Teaを営むYilingさんとPatrickさんは白い茶葉で作られた煎茶を持参し、さらに日本で開発された真新しいドリッパー「ときね」は完璧な出来栄えでした。試すのが待ち遠しいですね! 日本茶インストラクター・スペシャリストのOscar Brekellさんはわざわざ日本からこのフェスティバルに駆けつけたそうです。彼はオリジナルブレンドティー「Senchaism」コレクションを出展していました。さらに、彼は煎茶のワークショップを4回開催し、そこでは昔ながらの焙烙を使ったほうじ茶を炒るデモンストレーションで観客に感動を与えていました。 さらに、ドイツから参加のKEIKOではオリジナルセレクションである抹茶と煎茶の催しがありました。 上田流和風堂の練習生Flora Grimaldiさんは濃茶のデモンストレーションとともに、濃茶と薄茶の違いについて語りました。 日曜の午後、私たちは国際日本茶協会を紹介する機会がありました。Annaさんが私たちのミッション・5年間での活動と活躍を共有する中、他のメンバーは日本茶を観客に振舞いました。約40人がこのイベントの開催場である素敵なシアターロームに集まりました。彼らは私たちがコラボしている茶農家さんが作った3種類のお茶を堪能しました。最初にうてな茶屋のほうじ茶、続いて吉田茶園の和紅茶、最後にSAMURAI teafarm 牧之原山本園と勝間田開拓茶農協のアロマ煎茶を提供しました。 今回のフェスティバルを私はとても満喫しました。私たちのハイライトの一つはなんといっても温かいティーコミュニティでした。フェスティバルを通して、多くの私たちのメンバーに出会えたこと、そしてブースや講演中での彼らの積極的なサポートと活躍は素晴らしものでした。全体で22名の世界日本茶協会のメンバーがこのイベントに参加しました。ほとんどのメンバーはヨーロッパから参加し、時にはカナダから駆けつけてくださった人:Lee教授(私たちの初代メンバーの一人!)もいました。何人かは以前お会いしたことのある方々で、また再会できて嬉しかったです。その他のメンバーはオンラインでしか会ったことがなかったので、このイベントでついに対面で彼らと出会えました!!彼らとおしゃべりしたり、お茶を一緒にしたり、時にはディナーに行ったりと充実した時間を過ごしました。私たちは次のティーイベントを楽しみにしています!! Sofie Vercauterenさん, […]



29-CHABAKKA-TEA-PARKS-1.png)